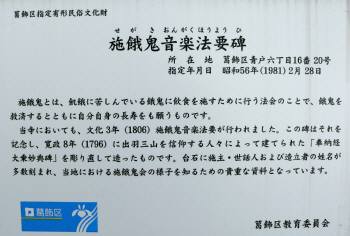春と秋に、春分の日、秋分の日をはさんで前後3日間ずつの一週間が「お彼岸」です。 法問寺では、入りの日と中日(春分、秋分の日)に、彼岸法要を行っております。 ◇ 彼岸とは・・・ サンスクリット語(仏教発祥地インドの言語の一つ)の、 パーラミタ―(波羅蜜多)を訳した言葉です。 また仏教では、お彼岸は悟りの世界を意味し、 煩悩に満ちたこちらの岸に対して極楽浄土の向こう側の岸(=彼岸)を表し、 毎日心がけて六波羅蜜の教えを実行する事により、その「極楽浄土へ渡れる」とされています。 しかし我々凡人は日頃忙しく、この有難い六波羅蜜の教えの毎日の実行は難しいので 「せめて年に2回、春と秋くらいはその教えを実行しましょう」 というのが、現在のお彼岸の意味になっています。 従ってお彼岸にはご家族揃ってご先祖・先亡霊位のお墓に冥福を祈ると共に、 生きている皆様は現在生かされていることを喜び この教えを実行し彼岸到達をめざしたいものです。 (六波羅蜜 ろくはらみつ) 布施 ・ ふせ : 奉仕の心を忘れない 持戒 ・ じかい : 規律や人との約束を守 る 忍辱 ・ にんにく : 不平不満を言わず耐え忍びましょう 精進 ・ しょうじん : 一生懸命努力しましょう 禅定 ・ ぜんじょう : 心を静かに保ちましょう 智慧 ・ ちえ : 物事を正しく判断する知恵をもつ ◇ |